第2話「予期せぬ祝福」
かつてこの大陸には様々な種族が共存していた。その中でも人間と魔族はお互いの能力や知恵を出しあい、とても良い協力関係にあった。
その絆の結晶のひとつが『魔石』である。
魔法の類を自由に操れない人間にどうやってそれを使えるようにできるかを考え、人間と魔族が数年かけて開発したその名の通り魔法の石である。
魔族はこの大陸にある無数の宝石類に目を付けた。宝石には元々微弱ながら魔力が備わっており、魔力を増幅させたりすることができ、魔界でも活用されていると言うのだ。
人間界の宝石は魔界ほどの魔力は備わってはいないがとても純度が高く、品質が高いらしい。魔族はその宝石の純度の高さから魔法を封じ込めようと考えた。
魔界でも魔石に魔法を封じ込めるという考えは昔からあったらしいが、魔界の宝石では魔力が高すぎたり、不純物が多かったりと安定して魔法を封じ込めるという事ができなかったという。その点人間界の宝石はとても純度が高く適切な宝石であった。
そうして生まれたのが魔石である。魔石には種類があり、一つの魔石により一種の魔法しか使えない。
しかし魔石を用いての魔法の発動も魔力を使用しなければ発現出来ず、それは魔力を扱えない人間には結局は扱えない代物だと思われた。
だが魔族いわく、人間にも微弱ながら魔力やそれに似た力が備わっているとの事でその扱いは簡単で少し学べば人間にも発動できるというのが魔族たちの考えだった。
そしてその考えは正しかった。勉強熱心な人間は魔族から講習を受け、センスがあるものは一瞬で、そうでない者もさほど時間がかからず魔石をつかった魔法の発現を可能にした。
こうして新たな文明を手に入れた人間界は瞬く間に発展していった。
しかし問題があった。魔法を封じ込めた魔石はその魔力はあまり長続きできず効力を失ってしまうのだ。そうするとまた魔族が魔法を封じ込め使えるようにしなければならない。魔族にもそれは流石に負担が大きすぎた。
しかしある人間の一言でそれも改善される事となったのだ。
「魔力が勝手に魔石に送りこまれたら魔族の皆にこんな面倒な事させずに済むんだけどなぁ」
その言葉で魔族達はハッとなった。精度の高い魔法を封じ込めるほどの純度はいらず、魔力を増幅させる事のできる宝石を用いればそれが可能なのではと思い付いた。
すぐさま魔族達は魔界から巨大な宝石を運び出し、その巨大な宝石に魔力供給の魔法を封じ込め数人で魔力を注ぎ込んだ。
魔力供給の魔法は下級の魔族でもできるくらい簡単なので純度はそこまで高くなくても封じ込めるらしく、さらには魔界の宝石の特性で少しの魔力を注ぐだけで何倍も魔力を増幅できるため魔族にも負担がない。
こうしてできたのが『大魔晶石』である。この大魔晶石と魔法を封じ込めた魔石をリンクさせる事によって大魔晶石の魔力が尽きない限りは、永久的に魔石へ魔力を自動で送り込む事ができるようになったのだ。
とは言え大魔晶石の魔力も永久ではない。大きさによって頻度は異なるが、だいたい数年に1回は魔族が魔力を注ぎこまなければいけない。
しかし毎回魔法を封じ込める作業に比べたら魔族の負担も天と地の差であった。
『大魔晶石レグルス』
現在、この世界においてたった一つとなった大魔晶石。その大魔晶石の前にミフユは立っていた。
「ふぅ…」
蒼色に輝くそれに触れていた手を離しミフユは一息つく。
「おつかれさん」
側で見ていた使い魔スティンガーがミフユに声をかけるとミフユは笑顔で「ありがとう」とかえす。
「ほんとは上級魔族の俺様がやってやってもいいんだけどな、このアホ魔晶石はお前らの家系の魔力しか受け付けねぇからな」
「別にたいして負担にならないからいいわよ」
「まぁお前に完全に任せてる親父も親父だけど」
「なんかパパはやりたがらないのよね、これ」
はて?と首を傾げるミフユだがあの気分屋の事を深く考えても仕方がないのでやめ、厳重に魔術で警備された地下室を後にした。
地上に戻ると、待機していたロゼッタが「おかえりなさいませ」と頭を下げる。
「おぅ!! ポンコツメイド!! 帰ったぜ!! 頭を下げるなんて良い心がけだな!!」
「おじいちゃんさんには頭を下げていませんわ!! それにポンコツでもありません!!」
「誰がおじいちゃんさんだ!!」
やいやいやっているのに構わずミフユはロゼッタに尋ねる。
「そういえばロゼ、結局パパたち昨日帰ってこなかったの??」
「あ、はい。そのようですわね」
「もー…外泊なんて聞いてないしー…」
「というか今現在も帰ってきておりませんわね…」
「あの親父二日ぶっ続けで飲んでるのか!!」
ギャハハと笑うスティンガーにミフユはため息をついた。
「そんな訳ないでしょ…ママも一緒なんだから。仕方ない。街に出て探しに行きますか。ロゼ、お供しなさい」
「かしこまりましたわ」
「んじゃ俺はもうひと眠りするわー」
そう言いながら各々その場をあとにした。
「今日も一段とにぎやかね」
「そうですわね。この活気こそがレグルス王国ですわ」
ミフユとロゼッタは街におり、国王たちを探しにきていた。
ミフユの言うようにレグルスの街は活気であふれていて、人が大勢いる。
もちろんこの活気があるのは世界にたったひとつしかない大魔晶石のおかげだという事はミフユもよくわかっている。
なぜこの世界にある大魔晶石がたったひとつでそれがレグルス王国にあるのかは文献も多く残されておらず、ミフユの父である獅子王も詳しくは知らないらしい。
絶対に何か知っているであろう魔族のスティンガーに聞いても「おぼえとらん」とはぐらかされミフユも深く考えるのはやめたのだ。
少ない文献の中に書いてあった情報によると、レグルス王国の創始者である魔族が大魔晶石のひとつを管理し、その大魔晶石とリンクをしてある魔石を人々に売り利益を得るというシステムを作ったらしい。
大魔晶石を独り占めして、しかもそれを人間に売りさばく。レグルスの創始者は意地汚いのかお金が大好きなのか…とミフユは常々考えていた。
そんな魔族の血が少しでも自分に流れていると思うと少し嫌な気持ちになる事もしばしば。
とはいえ、このシステムのおかげで今のレグルス王国があり、その収益で政策ができ、給金も払える。そして街に出ればお金をつかえる。他国との貿易もでき、他国からレグルスにはない色々なものも買える。自国にとっても他国にとってもとても良い感じにお金がまわっているのは確かである。
「そこに関しては感謝しないといけないのかしらね…」
おもわずそう口に出してしまったミフユに対して横で歩いていたロゼッタに「どうかなさいました?」と聞かれるが「なんでもないわ」と答える。
その後二人は世間話をしながら城下町へと脚を運び、レグルスいちの商店街へと入っていく。
しかしそこへ入った途端ミフユは不思議な体験をする。
顔見知った商店街の人々からひっきりなしに
「ミフユちゃん!!おめでとう!!」
と言われるのだ。
しかし言われている当事者のミフユも、隣を歩いているロゼッタも一体何の事かわからないのでる。
本当であれば理由を聞きたいのところだが、皆があまりにも満面の笑みである事と間髪いれずにおめでとうと言われるのでミフユも反射的に「ありがとう」と答えるだけで、何の事かと聞けなかった。
商店街は軽いパレード状態になってしまっていて困惑する二人は一度落ち着ける場所へと避難する。
二人が休日によく来るカフェへと入り席につきミフユはウェイトレスに「いつもの」と注文する。ロゼッタも続いて「わたくしもおなじものを」と注文する。
ウェイトレスがその場から「かしこまりました」と頭を下げ去って行ったのを見計らいミフユは口にする。
「この騒ぎは一体なんなのかしら…」
「そう…ですわね…ミフユ様なにかしましたか?」
「何もしてないわね…。誕生日でもないし」
「まだ春ですものね…」
四季のあるレグルスは現在春になったばかりである。夏生れのミフユの誕生日はまだ先なので、それが理由で祝福されているわけではないのは明白である。
「ひとつお伺いしてもよろしいですか?」
「どうしたの??」
「ミフユ様はなぜ夏生れですのに…その…お名前が…」
「あぁ…それね…」
ロゼッタの疑問はもっともである。ミフユの名前の『フユ』は季節の『冬』と一緒なのである。普通この文字を名前につかう場合冬生れが多いのだが、ミフユは太陽の日差しが眩しい真夏生れの夏女なのである。
「まぁそれを言ったらハルカも夏生れだけど」
「そこもずっと気になっていました」
そう、ミフユの幼馴染のハルカも『ハル』=『春』という名がついているがミフユよりちょっと早い夏生れなのである。
「もうそこはうちの親とハルカの親が頭悪いというか…」
はぁ…とため息をつくミフユだが、淡々とその理由をロゼッタに語り始める。
「獅子王…パパの名前は知っているわね?」
「はい、『ゾマーグ=レグルス=キサラギ』王様ですわ」
「そう、パパの名前のゾマーグの『ゾマー』って夏っていう意味なのだけど…パパは夏生れなの」
「はい、それは存じております」
「で、ハルカのパパの名前が『アキト=アマカセ』っていうのだけど、名前に秋ってはいってるでしょ?」
「夏と秋…ですか」
「そう。二人は幼馴染でずっと一緒だったんだけど、なんかお酒の席でいつも自分たちに子供ができたら春と冬を名前にいれようって盛り上がってたみたいよ」
「え…それで夏生れのお二人の名前は…」
「うん、こうなったのよ」
苦笑しながらまったく我々の親ときたらと首を振る。
「でも、お二人とも良いお名前だと思います。わたくしはとても好きですわ」
「あら、ありがとう。私もこの名前自体はとても気に入っているわ」
「そういえば…ハルカ様のご両親は…」
「うん、私たちが子供頃病気で亡くなっているわ。ロゼッタがここにくるだいぶ前ね」
「あっ…申し訳ありません…わたくしとしたことが…」
「いいのよ。知らなかった事だもの」
うぅ…とうなだれているところに注文したミフユとロゼッタお気に入りのピーチティーが運ばれてくる。
「おまたせいたしました、ミフユ様、ロゼッタ様。ピーチティーでございます」
ありがとう。と答えるとウェイトレスが続けてまたもあのセリフを言ってきた。
「そういえば、おめでとうございます。ミフユ様。昨日獅子王様たちもご来店なされたのですが、聞いた時私も自分のようになんか嬉しくて」
と満面の笑み。
「聞いたって…何を?? なんかさっきから商店街の人に同じ事言われて一体なんのことやら…」
と言いながらミフユは目の前のカップを手に取る。
「え…なんの事って…ミフユ様ついに戴冠なさるのですよね??獅子王様が今月中には戴冠式をすませてミフユ様を新国王にさせるって言いまわってますよ?」
「ふーん…私が新国王にねぇ…」
そう呟きながらピーチティを口に運ぶがそこでやっとミフユは言われた事を理解し始める。
「ぶっ!!」
気づいた時にはミフユの口の中に広がった桃の香り漂う上品な紅茶を目の前のロゼッタに吹きかけていた。
「きゃあ!!」
叫ぶロゼッタを意に介さずミフユがバンッと立ち上がり
「だ…誰が新国王に!? 今月中に戴冠式!?げほっげほっ…」
「だ…大丈夫ですか?ちょっと落ち着いてくださいミフユ様!! あぁ…ロゼッタ様、今拭くものおもちしますね!!」
「び…びしょびしょですわ…あぁでもなんていいますか…」
ミフユは呆然と立ち尽くしているが被害者のロゼッタはなぜか少し幸せそうであった。
「ご…ごめんね、ロゼ」
時間がたち少し落ち着いたミフユはロゼッタに申訳なさそうにする。
「いえ、大丈夫ですのでお気になさらないでくださいまし」
それより…と続けようとしたところミフユがぴくっと反応する。ロゼッタはこういう時ミフユの元にスティンガーから知らせが入ったという事を知っているので口を閉ざす。
ミフユと使い魔のスティンガーは魔力がリンクしているので、遠く離れた場所でもお互い連絡がとれるのだ。これも特殊な魔石をつかえば可能なのだが、この『念話』ができる魔石とその術式も中々高度で希少なものになっているため利用者は少ない。だがミフユたちはそれを魔石なしで行えるのだ。
『おねぇ様ーおっさん達帰ってきたぞー』
『わかったわ。今から帰る』
『ほーい』
と、こんな感じで言葉に発せずに会話できるのである。
「おじいちゃんさんですか?」
「えぇ、パパたち帰ってきたって。私たちも戻りましょうか」
「かしこまりました」
ロゼッタが会計を済ませ、二人は店を後にする。店から城に向かうまでの道のりで徐々にミフユの怒りは膨れ上がっていくのであった…。
レグルス城玉座の間では帰ってきたレグルス夫妻とルン達が和気あいあいと談笑していた。
「それでね!! ママ!! 今日もおじいちゃんがうるさくて…」
「誰がうるさいねん…スピー」
「あらあら~。スーちゃんおねむさんなのね~」
ルンがママと呼び、ルンの頭の上でつっこみながら寝ているスティンガーに話しかけるこの人がミフユとルンの母親である『サクラ=レグルス=キサラギ』である。
元々この『キサラギ』姓はサクラの旧姓であるのだが、サクラの両親の事を実の親のように思っている獅子王はどうしてもこの『キサラギ』という名を自身も名乗りたいという気持ちが強く、サクラと結婚する時にサクラの両親に許可を取り『キサラギ』の名を取り入れたのである。
「獅子王様、こんな大変な時に一体どこで何をしていらっしゃったのです?」
「え? 大変なの? まぁ色々あってな!!」
モーゼスが話しかけている獅子の顔をした黄金の兜…というか仮面を装着している人物がこの国の国王で皆から『獅子王』と呼ばれている『ゾマーグ=レグルス=キサラギ』である。
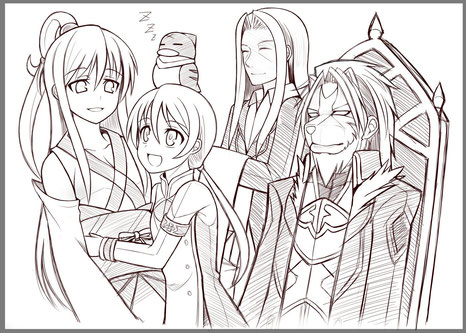
武芸は達者で人から好かれるようなおおらかな人柄ではあるのだが、やや能天気で面倒な仕事が嫌いという一国の主としては少し困ったところがあるのだが、それでも皆はこの男の事を心から慕っている。
「なんでもかんでもミフユ様任せでは…もう少々国王としてのお立場というものをお考えになった方がいいのでは?」
「あぁ…まぁその事なんだけどな…実は…」
獅子王がその先を言いかけたところでものすごい音をたてて玉座の間の扉が開く。
あまりにすごい音だったので、皆が一斉に扉の方へ振り向くと、もの凄い形相をしたミフユと慌ててミフユを追いかけているロゼッタが入ってきた。
ズカズカとミフユは父である獅子王の前まで詰め寄る。
「よぉ、ミフユ。おかえ…」
その言葉を遮るどころかかき消すかのように大声で
「一体どういう事なのよ!! パパ!!」
あまりに大きな声と迫力だったので、皆は驚き、ルンは固まりその頭上で寝ていたスティンガーも驚きのあまり転げおちる。
「あー…もしかして聞いちゃった??」
「聞いたわよ!!街の人たちにおめでとうって言われるからなんの事かと思ったら…」
「まぁまぁ…ミフユちゃん、とりあえずおちついて?」
「ママは黙ってて!!」
「うぅ…」
サクラがミフユをなだめようとするが一喝されて涙目になってしまう母サクラ。
「おいてめぇ!! サクラを泣かすなんてなんて事しやがる!!」
「うるさい!! 馬鹿親父!!」
「ミフユ様、少し落ち着いて事情を話していただけますか?」
モーゼスのその言葉でようやく少し落ち着きを取り戻したミフユは一度ふぅーと息を吐き説明をはじめる。街であった事、カフェで言われた事の全てをその場にいたモーゼスたちに話した。
「なるほど…それは怒るのも無理ありませんね。一体どういうおつもりで?獅子王様」
話を聞いたあとにモーゼスは獅子王に問いただす。
「いやぁ~。だってよ、実質今国の仕事してるのってミフユだろ? だったらさっさと正式に全部任せてもいいかなってよぉ」
「いいかなって…その本人である私に相談もせず決めるの?」
「いいじゃねぇか、だって俺国王だもん」
「この…そういう時だけ国王とか言って…」
「まぁ勝手に決めたのと、街で言いふらしてたのは謝るけどよ」
「じゃあ今すぐ謝ってよ」
「え、やだ」
「なんなのよ!!」
いらつくミフユに再びサクラが間をわって入ってくる。
「まぁまぁミフユちゃん。パパも色々考えがあっての事なのよ?」
「考え?」
「そうなのよ。ちょっと気になる事があってね。ちょっと当分国を離れようと思うの」
「え?」
「そうそう!!ちょっとママと大陸と4つの島をめぐる旅行しようと思ってな!!」
「もう!!あなた!!いい加減にしないと流石のサクラも怒っちゃいますよ!!」
「う…すまん…」
流石にふざけすぎたのか、サクラに怒られてうなだれる獅子王。
しかしその二人の空気にミフユとモーゼスは何か感づいたのか、二人に向かって静かなトーンで問いかける。
「もしかして…最近の異変の調査…?」
その言葉に獅子王とサクラは目を合わせ頷く。
「あぁ、ここ最近のこの大陸での異変でちょっと気になる事があってな」
「気になる事?」
「…すまんが詳しくはまだ言えんのだ」
先ほどまでふざけた空気とは違ったのでミフユはそれ以上詳しく聞くのをやめた。
「とりあえずこれは俺とサクラにしかできない事なんだ。だから当分国を離れなくちゃいけない。しかしそうなると」
「長い間国王が不在になる可能性がある…ですか」
「あぁ」
モーゼスの言葉に頷く獅子王だが、ミフユはあまり納得いってない。
「だからって私が今跡を継がなくてもよくない? 代理とかそういうのでも…」
「うーん…丁度いい機会だと思うんだけどな。どう思う? モノズキ、スティンガー」
獅子王はモーゼスとルンの頭から転げ落ちたあとになんか真面目な話してるな、とりあえず黙っとくかと再びルンの頭の上に乗り静観していたスティンガーに聞く。
「別にいいんじゃね? 交代で」
「私もこれが良い機会だと」
適当なスティンガーと笑顔のモーゼスにそう言われ複雑な心境のミフユである。
「でも…だからって急すぎる…」
「なんだ珍しくびびってんのか?」
「びびってないわよ!!」
「大丈夫。お前ならできるさ。俺とサクラの娘なんだからな!!」
「く…」
「それにもう国の皆には言いふらしてきちゃったし!! みんなお前の事頼りにしてたぞー!!」
「ぐぬぬぬ…」
「流石、ミフユ様の性格をよくわかってらっしゃる。こうなる事を見越しての言いふらしでしたか」
モーゼスが言うようにこれは獅子王の作戦であった。おそらく先にミフユに話していたら頑なに引き受けなかったであろう。しかし、人々から期待されたり頼まれたりすると断れないで張り切ってしまうミフユはこの現状では絶対に嫌とは言えないのである。
「中々下衆いなおっさん…だが嫌いじゃないぜ」
と言うスティンガーにたいして獅子王は「だろ?」と答え、お互いなぜかサムズアップ。
心配そうに見つめるロゼッタの横でぐぬぬと唸っていたミフユであったが、流石にもう逃げ道はないと観念したのか
「あー!! もうわかったわよ!! やります!! やればいいんでしょう!!」
と大声をあげる。
「よし!! じゃあ決まりな!! もろもろの日程とかはあー…モノズキとロゼッタ頼むわ!! あと…ん? ハルカのやつは?」
「今日は休暇で朝からカジノ」
ミフユがふてくされたように言う。
「あいつも好きだな~」
普段はだるそうにしながらも几帳面に仕事をしているハルカだが、なぜかギャンブル好きで休暇があると大体カジノに行くのである。
「まぁそういう事だからよ、あとは頼んだぜ!! …という訳でスティンガー、久々に飲み行くか!!」
「うぇーい!!」
昨日も飲みに行ったのだから少しは仕事しろ…と言いたかったがミフユはもうため息しかでなかった。そんなミフユにサクラが声をかける。
「ミフユちゃん、ごめんね?」
「えぇ…ママ。大丈夫よ、ちゃんとわかってるから。ただちょっと急すぎたから…」
「そうよね。でもミフユちゃんなら立派な女王様になれるわよ~!!」
「女王様ってなんかちょっと嫌な響きね…」
「ん??」
「いや、なんでもないわ。ところでルンはいつまで固まっているのかしら」
「あら~」
口を開けて固まっているルンをサクラはニコニコしながら頬に手をあて眺める。さきほどのミフユの怒声に驚いて固まったまま動いてない。
「ルンちゃ~ん♪ 朝ですよ~♪」
そう言いながらサクラは楽しそうにルンの頬を指でつんつんする。
「はっ!!…あれ? ママ、おはよぉ!!」
「はい、おはよぉ♪」
「おはよぉ♪ …じゃないわよ二人とも呑気なんだから…」
そしてまたため息をつく。現状を理解していないルンは首を傾げるしかないのだが、ミフユは帰ってきてからというもの怒るかため息しかついてない。
「ミフユちゃん、そんなにため息ついたら幸せ逃げちゃうわよ?」
「え!! おねー様の幸せ逃げたら大変!!」
母娘できゃっきゃうふふと騒いでいる。ミフユもいつもだったら仲間に入るのだがそんな気分には全くなれない。今のミフユの心情を理解しているのはおそらく、モーゼスとロゼッタくらいであろうか。ロゼッタはただただミフユの現状を心配していて、モーゼスはこの国とその周辺の現状を考えればミフユが王になるという事はベストなのかもしれないと考えている。そして今後ミフユが背負う重圧と責任は相当なものだろうと心配はしているが、ミフユならなんとかなるという気持ちもあり、従者としてこれからも全力でサポートしていこうという気持ちが強かった。
春は出会いと別れの季節。まさか自分の王の娘という立場と別れ、女王になる事が決定しようとは思ってもみなかったミフユであった。
そしてミフユの幼馴染の春はそんな冬の気持ちを知る事もなく遊んでいた。
「よっし!! また私の勝ち!! 今日は私ついてるなー!!」
ミフユが正式に女王になったら自分も忙しくなるという事を知る由もなく・・・
